四十九日法要のお布施を完全解説!相場・地域・宗派を詳しく紹介!
(2021/4/5 情報更新)
読経を行い、故人を供養してくださったお礼として僧侶に渡すお布施。
もちろん、葬儀・告別式以外の四十九日法要などでも準備しておく必要があります。
このとき渡す金額などは法要ごとに若干変わってくるので、正しい相場で渡せるように、あらかじめ四十九日法要における相場などをしっかり覚えておきましょう。

四十九日とは?
そもそも四十九日とはどのようなものなのでしょうか?
四十九日法要とは?
四十九日法要とは、仏教における「忌日法要」の一つのことです。
故人が亡くなった日から7日ごとに行われる法要のことを忌日法要と呼んでおり、四十九日法要はその一番最後に当てはまります。
地域によっては「七七日」と呼ぶこともあり、読み方は「なななぬか」「しちしちにち」「なななのか」など様々です。
四十九日法要は最も大切な忌日法要
この四十九日法要は、故人やご遺族にとって最も大切な日とされています。
なぜなら仏教においては、四十九日を超えると故人が仏様のところへ旅立つといわれており、同時に極楽浄土へ行けるかどうかの判断が下される日とされているからです。
一般的な四十九日法要では、仮の白木の位牌から本位牌へ故人の魂が移るのに伴い納骨も行います。
四十九日法要を行う日
基本的に四十九日法要は、四十九日が経った当日に行うのが理想です。
しかし大勢の方に集まってもらうことを考えると、平日開催は難しい場合がほとんど。そのため現在では、四十九日を迎える直前の土日や祝日で行うのが一般的です。
四十九日法要を行ってはいけない日
逆に四十九日を過ぎてから法要は行うことは避けましょう。
なぜなら、四十九日を超えるとすでに仏様の元へ旅立っていると考えられるため、本来の意味とはずれてしまうからです。
また、亡くなって3ヶ月が過ぎてから四十九日法要を行うことも避けましょう。
なぜなら、語呂合わせのような感じで「始終苦(四十九)労が身(三)につく」という風に考えられているためです。
あくまでも伝統や風習のようなものではありますが、どのみち長く供養を放置しないためにも四十九日法要は早めに行うべきです。
四十九日法要では六曜は意識しなくてもよい
葬儀のときは、六曜の「友引」を避けた方が良いと言われています。故人の宗派が仏教や神教だった場合は、昔からの風習として友引に法要を行うのを避ける方も多いようです。キリスト教の場合は六曜は意識する必要はありません。
法要の際に、六曜を意識する人はほとんどいませんが、念のため開催日や親族を相談した方が無難でしょう。基本的には親族が集まりやすい土日などに開催されることが多いです。
葬儀の日取りについては「友引に葬式が行われない理由とは?葬式の日取りの決め方についても解説」の記事もご参考ください。
忌中・忌明けとは?
この四十九日法要と関連して、「忌中」「忌明け」という言葉も頻繁に耳にするかと思います。
忌中とは?
まず「忌中」とは、故人が亡くなってから四十九日まで喪に服し、身を慎むための期間のことです。
神道では「五十日祭」と呼ばれています。忌中はもともと仏教とは関係の無い言葉であり、神道における「死は穢れているもの」という考えから生まれたものです。
忌中の期間は死の穢れがまだ強いとされているため、家にこもって故人のために祈ることで穢れを祓うという目的があります。
結婚式や新年のお参りなどの祭り事には参加せず、神社へのお参りなども控えるのが一般的です。
忌中の期間は仏教と神道で若干の違いがあります。
仏教では四十九日法要を区切りとして忌中が終わりますが、神道では故人との関係の深さによって期間が異なるのです。
最大で50日になることもあり、そのため五十日祭と呼ばれるのですね。
喪中とは?
ちなみに似たような言葉に「喪中」があります。こちらも喪に服すという意味では一緒。しかし期間は忌中よりも長く、最大で1年間喪中になることもあります。
忌明けとは?
そして「忌明け」とは、上記の忌中や喪中の期間が終わること。
この忌明けの日に四十九日法要を行うことがほとんどです。このタイミングで遺骨の埋葬や納骨を行うこともあります。
忌明けの返礼品
葬儀・告別式でいただいた香典やお供え物のお返しは、この忌明け後のタイミングで渡しましょう。これを「忌明けの返礼品」とも呼びます。
品物に関して特に縛りはありませんが、日持ちしない生ものや刃物などは選ばない方がいいでしょう。
すぐに消耗できる日用品やお菓子などを渡す場合が多く、最近ではカタログギフトから好きなものを選んでもらうケースも増えています。
品物の値段は香典の半額程度であることが多いですが、葬儀当日にある程度の金額を渡していたり(即日返し)、地域によっても変わってくるので多少の変動はあるでしょう。
このお返しには「忌明けの挨拶状」も添えます。ここには参列していただいたことへのお礼や、四十九日法要を行えた旨などを記載しましょう。
喪中・忌中については「喪中に神社へ行ってもいいの?喪中と忌中の違いから厄払いやお守りの処分の方法などを徹底解説!」「喪に服すとは?意味と期間と宗教と寺社と注意点・マナーを徹底解説!」の記事もご参考ください。
追善供養とは?
「追善供養」とは、生きている方が故人に対して供養を行う行為のことです。
広い意味では、仏壇に手を合わせてお茶を供えたり、お墓参りをすることも追善供養の部類に入ります。
しかし一般的には、「一周忌などの法要・法事を行うこと」そのものが追善供養と呼ばれることが多いです。
具体的には「生きている方が現世で善い行いをすることによって、故人が生前に犯してしまった悪行を軽減させることができ、徳が増すことで極楽浄土へと逝ってもらえる」という意味合いを持ちます。
生きている方の善行が故人の善行になる、という考え方なのですね。
追善供養の儀式には主に2つの種類があります。それが「中陰供養」「年忌法要」です。
中陰供養とは?
まずは「中陰供養」についてです。「中陰」とは亡くなった日から四十九日が経つまでの期間のことであり、その間に7日ごとのスパンで行われる法要が「中陰供養」です。
具体的には「初七日」「二七日」などといわれる法要のことを指しています。
なぜ7日ごとなのかというと、「故人は四十九日までの間、7日ごとに閻魔大王によって極楽浄土へ行けるかどうかの裁きを受けている」という考えに基づいているためです。
追善供養を行い生きている方の善行をあの世へ送るという行為を通じて、無事に良い判断が下されてほしいという願いが込められているのです。
初七日については「初七日とは?意味・数え方・お供え・お経・知っておきたい常識とマナー」の記事もご参考ください。
年忌法要とは?
「年忌法要」とは、亡くなった日から数えて節目の年に行われる法要のことです。
一周忌や三回忌、七回忌などがあります。
一周忌に関しては亡くなってから満1年目に行いますが、三回忌以降は「亡くなった年を含んで数える」というのが一般的です。
したがって、三回忌の場合は2年目に、七回忌の場合は6年目に、十三回忌の場合は12年目に法要を行います。
基本的には年忌法要全てを盛大に行うことはありません。
参列者を招待し僧侶の読経も行うような式は三回忌で終わることがほとんどです。
それ以降は規模も小さくなり、ご遺族だけで式を行うことが多いです。宗派による違いはありますが、三十三回忌や五十回忌で弔い上げとなります。
年忌法要については、下記記事をご参考ください。
・一周忌とは?意味・香典・お布施・お供え・マナーを完全解説!
・三回忌のお布施を完全解説!金額相場・書き方・渡し方・喪主・参列者のマナーを紹介!
・七回忌とは?意味とお布施・香典の相場と出席マナーを解説!
・13回忌とは?13回忌の準備から招待された場合のマナーまでを完全解説!
宗派ごとでの違い
四十九日法要の基本的な流れ自体に大きな違いはありません。しかし細かい面では多少宗派に合わせる必要があるので注意しましょう。
例えば、曹洞宗の場合は複数の僧侶が四十九日法要に参加する場合があります。
また、四十九日法要後に安置する御本尊もお葬式同様、宗派ごとで異なります。
例えば、浄土真宗では「阿弥陀如来絵像」が御本尊で、日蓮宗では「曼荼羅」が御本尊です。
こうした細かい点は専門知識が無いと知りようがないので、僧侶や仏具店にあらかじめ相談しておきましょう。
ただし、「仏教」「神道」「キリスト教」という大きな枠で考えると大きく違いがあります。
◎仏教
仏教では法要を行う年があらかじめ決まっています。それが四十九日や一周忌、三回忌などの法要ということですね。この法要は命日を迎えるよりも先に行います。
◎神道
神道には法要がありません。その代わりに「霊祭」という行事を行います。
最初に行うのは、葬儀・告別式の翌日に行う「翌日祭」です。そこからは10日ごとに「十日祭」という行事から始めて、「五十日祭」まで行います。
ただし最近では、二十日祭と四十日祭は行わないことが多いようです。この行事では、故人が好きな食べ物をお墓に供えてお参りします。
◎キリスト教
キリスト教にも法要がありません。その代わりに、亡くなった日から3日目・7日目・30日目などに「追悼ミサ」を行います。
追悼ミサではご遺族や友人が教会に集まり、聖歌を歌ったり神父のお話を聞いたりすることがメインです。
ちなみに上記の日数には特に決まりが無いため、仏教の四十九日などに合わせることもあります。
四十九日の流れ

ここまでで四十九日法要に関する基礎的な知識をご説明してきました。それではここからは具体的な四十九日法要の流れについて見ていきましょう。
四十九日法要までに準備・手配すること
四十九日法要までに準備・手配することをご紹介します。
◎日程と会場を決める
まず葬儀を終えたら、なるべく早めに日程と会場を決めます。行う日は先述の通り、四十九日を迎える直前の休日がベストです。
同時に会場も決めておきます。自宅・寺院・斎場・ホテルなどを選ぶ方が多いです。ご自身の予算や参列者の数などを考慮して決めてください。
参列者や僧侶の予定もあるので、1ヶ月前までには決めておきましょう。
◎寺院に連絡
そして、日程が決まり次第寺院に連絡します。僧侶の予定も関係してくるのでなるべく早めに伝えましょう。
特にお盆周辺の時期などは忙しい可能性が高いため、早めに予定を固めておかないと日程がずれるかもしれません。
後からバタバタしないように、葬儀の段階で僧侶と相談しておくのもいいでしょう。
◎会食の手配
四十九日法要後の会食の手配も忘れずに行います。寺院や斎場で行う場合は、斎場の専用部屋で食べるか近くの料亭に行くことが一般的。
自宅で行う場合は仕出し料理を手配することもあります。ただし場合によっては会食を行わず解散しても問題ありません。
その場合は参列者にお弁当とお酒を持ち帰ってもらうことになります。形式が違うにしても、料理の準備を行うことがほとんどということですね。
ちなみに料亭を予約するときは、必ず「法要で使う会食である」という旨を伝えておきましょう。
この一言がないと、伊勢海老や鯛などのお祝いごと用の食材が使われる可能性があるためです。
法要時の会食については「おとき(お斎)とは?意味とマナーと香典相場を3分で解説!」の記事もご参考ください。
◎参列者へ連絡
参列してもらう方の範囲も決めておきましょう。故人の意思で「遺族のみで法要を行ってほしい」などがある場合を除いては、親族を全員招くのが一般的です。
会食の予約やお返しの品物を準備する関係もあるので、出欠は往復ハガキなどで返してもらいましょう。
◎(納骨を行う場合は)「本位牌」の準備
四十九日法要と合わせて納骨を行う方も多いです。その場合は「本位牌」も準備しておきましょう。
先述の通り、四十九日法要で仮の白木の位牌から本位牌に魂が移ると考えられているためですね。仏具店で購入することができます。
本位牌には以下のことを彫り込みます。
この本位牌の彫り込みを注文すると完成まで1〜2週間ほどかかるため、早めに依頼しておくことがオススメです。
ちなみに本位牌は忌明け後に仏壇に納め、白木の位牌は寺院に渡します。
納骨については「納骨のお布施を完全解説!金額相場・書き方・渡し方・マナーを紹介!」「納骨にかかる費用を完全解説!相場・内訳・流れ・準備物を紹介!」の記事もご参考ください。
◎(必要に応じて)お墓の手配
納骨を行う際は先祖代々のお墓に納めるのが一般的です。ただし、まだお墓がない場合は、四十九日法要までに霊園や寺院に建立しておく必要があります。
お墓の手配には早くても1ヶ月程度かかることが多いので、葬儀後速やかに手続きしておきましょう。
もし間に合わなければ、完成してからの納骨となります。納骨の際には「埋葬許可証」が必要なので忘れずに持参してください。
埋葬許可証については「埋葬許可証の意味とは?発行から提出までの流れや紛失時の対処法を解説」の記事もご参考ください。
当日の流れ
四十九日法要当日は以下のような流れで行います。
◎開式の挨拶
まず参列者が全員着席したら僧侶を仏壇の前に案内します。そうしたら喪主が挨拶を行い開式です。
挨拶で述べることはあらかじめ挨拶文として紙に書いておくと内容を間違わなくて便利でしょう。
◎読経とご焼香
喪主の挨拶後に僧侶の読経とご焼香を行います。ご焼香は僧侶の合図で開始しましょう。順番は「喪主→ご遺族→友人・知人等」です。
◎僧侶の説話
読経とご焼香をしたら僧侶の説話を聞きましょう、説話では仏法に関すことをはじめ、身になるようなありがたいお話を聞くことができます。
◎位牌の閉眼&開眼供養
「閉眼供養」とは、故人の魂が入っていた物からそれを引き抜くための法要のこと。
「開眼供養」とは、その魂を新たにどこかへ入れるための法要のことを表します。仏教ではその入れ物が位牌なのですね。
葬儀の時点では、仮の入れ物として白木の位牌に魂が入っているとされています。
その白木の位牌から本位牌へと魂を移すのが、この「閉眼&開眼供養」なのです。本位牌は基本的に黒い漆塗りであることが多いです。
◎納骨とお墓参り
上記が終わったらお墓で納骨を行います。この「納骨法要」はいつまでに行うかという明確な決まりはありません。
しかし現在では四十九日法要と同じタイミングで行う方が増えています。
これは、ご遺族や親族がすでに集まっている段階で行なった方がスケジュール的にも負担が少ないためです。
ただしお墓や納骨堂が無い場合は後日になります。一周忌法要と合わせる方も多いようです。
納骨の際には「埋葬許可証」が必須。死亡届を提出すると発行されるので、納骨法要も行う場合は必ず準備しておきましょう。
死亡届については「意外と知られていない「死亡届の提出方法」につい徹底解説!」「死亡届の基礎知識を押さえておこう!書き方やその他の手続きについても解説」の記事もご参考ください。
◎会食
全ての法要が終わったら会食をいただきます。食べ始める前には喪主から2度目の挨拶が行われることが多いです。
場所を変える必要がある場合はスムーズに案内できるようにしておきましょう。
◎香典返しやお布施を渡す
会食後にタイミングを見計らって、香典返しやお布施を渡します。お布施を渡すタイミングに関しては、あらかじめ僧侶と相談しておくといいでしょう。
香典返しについては「香典返しのマナーを完全解説!相場・時期・挨拶状・例文・品物も紹介!」の記事もご参考ください。
四十九日法要の服装
四十九日法要での喪服についてご紹介します。
喪主の場合は最も格式が高いとされる正喪服の着用が望ましいです。男性女性共に、黒のフォーマルスーツになります。ただし、最近では葬儀の簡略化が進んだことにより、準喪服でも問題ないとされています。
参列者も3回忌が終わるまでは、正喪服もしくは準喪服が望ましいです。3回忌以降は略式喪服でも問題ありません。
喪服については「ユニクロで喪服を用意できる?ユニクロで喪服を用意する際のメリットやデメリット、注文方法を完全解説!」「急な葬儀での服装はどうする?注意点の多い女性の喪服を徹底解説!」もご参考ください。
四十九日法要の持ち物
喪主・施主の持ち物
四十九日法要を開催する喪主側の持ち物をご紹介します。
●お布施
●遺影
●(納骨式を行うのであれば)埋葬許可証
●位牌
●参列者への引き物
法事・法要の持ち物については「法事とは?日程とお布施と服装持物を徹底解説!」の記事もご参考ください。
参列者の持ち物
四十九日法要に参加する際の持ち物についてご紹介します。
お布施とは?
.jpg)
以上が四十九日法要における基本的な流れなどです。では、最後に渡す「お布施」とは具体的にどのようなものなのでしょうか?
現代では「読経をあげていただいたお礼として僧侶の方に渡すお金」という認識が広まっています。
今は現金が主流ですが、昔は経済的な理由で現金を渡せない家庭もあったので、その場合は骨董品や食料などを渡していたそうです。
渡す物は変化していますが、供養を行ってくれた僧侶への感謝の気持ちを表現していることには変わりがありません。
お布施を渡す理由
ちなみにお布施は、寺院への寄付金としての役割も担っています。
寺院には御本尊が設置されているため、お布施を通じて間接的に私たちがそれを支えているということですね。
ではなぜお布施が感謝の気持ちを表現する物として定着したのでしょうか?もともとお布施というのは、仏教の「六波羅蜜」という修行の一環でした。
この六波羅蜜とは「布施」「持戒」「忍辱(にんにく)」「精進」「禅定」「智慧(ちえ)」の6つ。
この徳目を得ることで悟りの境地に達することができるといわれていました。
この中の1つである布施には「見返りを求めず他人に何かを与える」という意味があり、これはさらに「財施」「法施」「無畏施」の3種類に分けることができます。
この財施は「金銭などの形あるものを与える」ということなので、それがお布施という形になって現代の慣習になっているのです。
また、上記の法施には「釈迦の教えなどを説いたり、読経を行うこと」という意味があります。そのため僧侶が行う読経は法施に当てはまるということですね。
お布施については「3分で分かる法事のお金の相場(香典・お布施):お金の入れ方と袋の書き方!」「法事とは?日程とお布施と服装持物を徹底解説!」もご参考ください。
四十九日のお布施の相場
では四十九日法要ではどのくらいのお布施を渡すのが一般的なのでしょうか?
特に定価が決まっているわけではありませんが、感謝の気持ちを表す物なのである程度の金額を準備する方が多いです。
一般葬の場合
一般葬後の四十九日法要の場合、3万〜5万円が相場といわれています。
葬儀・告別式よりも低い金額になるのが一般的です。ただし、寺院との関係性や(後述しますが)宗派、地域によっても若干の変動はあります。
ちなみにこの相場は四十九日法要と一周忌に関するもの。基本的には亡くなった日から遠い日程の法要(三回忌、七回忌など)になるほど、お布施の相場は下がっていきます。
一般葬については、「仏式葬儀とは?一般的なマナーや葬儀の流れについて徹底解説」をご覧ください。
葬儀形式が異なる場合
では、今少しずつ広まっている火葬式や家族葬、一日葬などの違う葬儀形式ではどうでしょうか?実は葬儀形式が変わってもお布施の相場はほぼ一緒。
僧侶の方に読経してもらうということに変わりはないので、同程度の金額を渡すことが多いです。
ただし、火葬式などは無宗教の方が行う場合もあるため、そもそも僧侶を呼ばないこともあります。その時は特にお布施を用意する必要がありません。
<各葬儀についての参考記事>
●家族葬
・家族葬とは?流れ・費用・マナー・選ばれる理由を完全解説!
・あなたもきっと勘違いをしている「家族葬の本当の意味」
●1日葬
・葬儀の1日葬とは?1日で行うお葬式の特徴について
・色々なお葬式の形 一日でお葬式を行う「一日葬」とは?
●直葬
・直葬とは?流れ・費用・マナー・選ばれる理由を完全解説!
・火葬式を完全解説!費用・流れ・マナー・香典・一般葬儀との違いを紹介!
●密葬
・密葬とは何?密葬を行うメリット・デメリットなどを徹底解説
付き合いのあるお寺によってお布施の金額が異なる場合も
葬儀形式以外にも、お寺によってはお布施の金額が変わる場合があります。
例えば、格式の高いお寺の僧侶に法要をお願いした場合や、普段から密な関係をとっていてよく寄進(寄付)しているなどといった場合は、相場よりも高いお布施をお渡しすることが多いです。
具体的には、お寺の格式が一番高い「総本山」などに頼んだ場合や、代々先祖のお墓を供養してもらっている菩提寺(檀那寺)など長い付き合いがあるなどといったときです。
また、地域にその宗派の信者が少ない場合も、お寺の維持費の為にお布施の額が高くなる傾向にあります。
普段、お寺とのお付き合いがほとんどない場合は、一般的なお布施の相場をお渡しすることになります。
昨今は、特にお寺とのお付き合いも薄くなってきており菩提寺を持っていない方も多いです。その場合は僧侶手配サービスを利用することもできます。
『やさしいお坊さん』でもご相談を受け付けております。追加費用が不要でお車代、御膳料、お心づけなども必要ありません。
四十九日法要のお布施の金額相場(宗派別)
次は宗派ごとにおけるお布施の相場です。
宗派ごとでの金額相場
ここでは主な7つの宗派における相場についてご紹介します。
◎浄土真宗
浄土真宗では「葬儀・告別式に渡したお布施の1割」あるいは「年収の1%」が相場といわれています。そのためだいたい3万〜5万円くらいになることが多いですね。
◎浄土宗
浄土宗は3万〜5万円くらいが相場です。
◎真言宗
真言宗は3万円くらいが相場です。
◎曹洞宗
曹洞宗は若干幅が大きく3万〜10万円くらいが相場です。なぜ幅が大きいかというと、場合によっては複数の僧侶が法要に参列するケースもあるため。
そのことを考慮すると、どうしても単独の場合よりも高くなります。
◎臨済宗
臨済宗は3万〜5万円くらいが相場です。
◎天台宗
天台宗は3万〜5万円くらいが相場です。
◎日蓮宗(法華宗)
日蓮宗は5万円くらいが相場です。他の宗派とは違い「読経1回につき5万円」という金額がある程度定まっています。
宗派ごとで相場が異なる理由
上記のように、そこまで大きい差はなくとも若干金額の変動はあります。
これは、宗派によっては卒塔婆や本位牌を準備する必要があるため。それらの金額も加味されているため若干の変動があるのです。
また、曹洞宗のように複数の僧侶が法要に関わったり、日蓮宗のように読経1回ごとの金額が決まっていたりと、その宗派の慣習にも左右されますね。
寺院との関係性も考慮しなくてはいけません。付き合いの深い寺院であれば20万円ほど渡すことあるので、むしろそういった面が金額に大きく関わってきますね。
四十九日法要のお布施の金額相場(地域別)
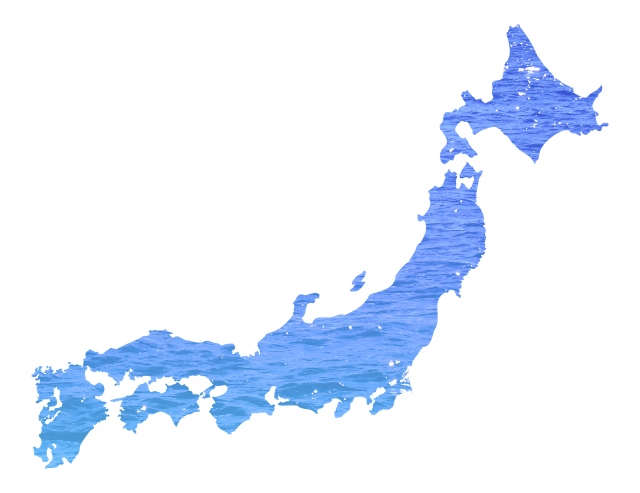
続いては地域ごとにおけるお布施の相場です。
地域ごとでの金額相場
地域別で見ると、「北海道や東北などの東日本が3万5千〜4万5千円程度」「関東が5万円程度」「西日本が3万〜4万5千円程度」の相場となっています。
こちらもそこまで大きな差があるわけではありませんが、若干の変動はあるようです。
地域ごとで相場が異なる理由
関東は人口が多いため、依頼が集中しやすい傾向にあります。東京などは物価も高いので、お布施の金額も影響する傾向があります。
とはいえ、もともとお布施の相場自体が3万〜5万円程度なので、そこまで大きな差は出ないでしょう。
四十九日法要でお布施以外に渡すお金
四十九日法要では、必要に応じてお布施以外のお金も渡します。それが「御車代」「御膳料」です。
御車代
まず御車代は、僧侶を自宅などの寺院以外にお招きした場合に渡します。
金額相場は5千〜1万円くらいが一般的です。
これは移動距離に対して渡すというよりも、僧侶への感謝の気持ちなのでこれよりあまりにも安い金額は避けるべきです。
ただし、喪主の方が僧侶の送迎を行なった場合などは渡す必要はありません。
もしも遠方から招いた関係で宿泊が必要になった場合は、その宿泊代も御車代にプラスして渡しましょう。
御膳料
そして御膳料は、法要後の会食に僧侶が出席しない場合に渡します。
金額は会食の内容によって変動するのですが、5千〜2万円くらいの幅で渡すことが多いです。
そもそも会食の予定が無い場合は、参列者と同じく折り詰めなどを渡しておけば大丈夫です。
御膳料については「御膳料とは?相場と渡し方と注意点とマナーを解説!」の記事もご参考ください。
四十九日法要と納骨法要のお布施
これに加えて、四十九日法要と同日に納骨法要を行う場合は、それに対するお布施も準備しておきましょう。
相場は3万〜5万円くらいです。渡すときは同じ袋に入れても問題ありません。
上記の納骨法要を行う際、宗派によっては卒塔婆が必要な場合もあります。
そのときは卒塔婆に対する費用も渡さなくてはいけないため、あらかじめ寺院に詳しい金額を聞いておきましょう。
卒塔婆の費用は、白い封筒に「御卒塔婆料」あるいは「御卒塔婆供養料」と書いて僧侶に渡します。
「お車代」「御膳料」などのお布施はそれぞれ別に包んでお渡しする
上記にご紹介したお車代や御膳料、納骨法要のお布施は僧侶にお渡しするタイミングは、同じで問題ありません。
ただし、封筒はそれぞれ別に包んでお渡しするように注意が必要です。表書きもそれぞれ「お車代」「御膳料」「入魂御礼」など分けて記入するようにします。
四十九日法要でのお布施のマナー
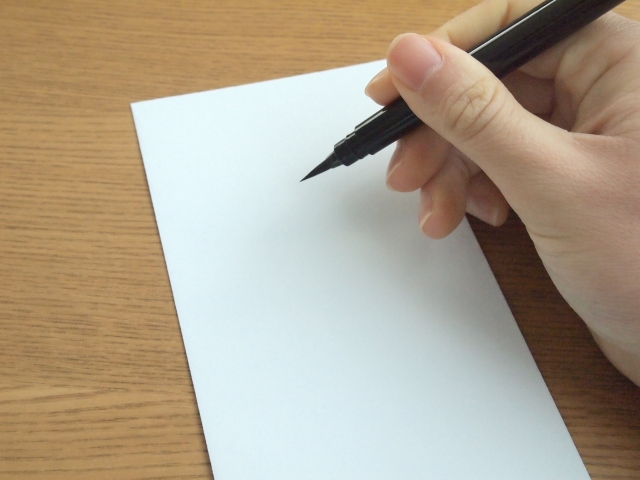
それではここから、四十九日法要におけるお布施の主なマナーについてご紹介します。
ただお金を渡せば良いというものでは無いので、きちんとした包み方や渡し方を覚えておきましょう。
封筒の選び方
お布施は、現金を封筒に入れて僧侶に渡します。
この時に使う物は、郵便番号欄の無い無地の白い封筒、あるいは「お布施」の文字が印刷された専用の封筒です。
ただし封が二重になっている封筒を使うのは避けましょう。なぜなら「不幸が二重に起こる」という意味を持ってしまうため。
また、熨斗袋はお祝いごとで使う袋のため、法要で使うのはマナー違反です。「御車代」「御膳料」などは別の封筒を用意しておきましょう。
包み方
基本的にはそのまま封筒に入れて渡しても問題はありません。
しかし、より丁寧に渡したい場合は、奉書紙(ほうしょがみ)という白い紙で包むといいでしょう。
その際は、まず半紙でお札をくるんでから奉書紙で包んでください。半紙がなければ中袋にお札を入れてからでも大丈夫です。
奉書紙はツルツルしている面が表なので、包むときは裏側を上にしてください。
包むときは、奉書紙裏側の真ん中より少し左側に中袋や半紙を置き、「左→右→下→上」の順番で折っていきましょう。
水引は基本的には使用しない
四十九日法要では上記のように封筒や奉書紙を使用するため、水引は基本的には使用しません。
理由としては、法事は厳密には弔事では無いためです。ただし、中には弔事と考える方もいる為、水引が印刷された封筒が使用される場合もあります。
もし使用する場合は、色は白黒で結び切りもしくはあわじ結びになっているものを選びましょう。
お札の入れ方
お札は人物画が描かれている方を上に向け、袋の入り口側に人物画が来るように入れてください。
取り出したときに人物画から先に見えるようにするということですね。複数枚入れるときはきちんと向きを揃えておきます。
通夜などでは「突然の訃報でキレイなお札を用意できなかった」ということを示すために新札を避ける傾向にあります。
しかし四十九日法要はすでに予定が決まっているのでなるべく新札を入れましょう。複数枚入れる場合は、なるべく新札の数が多くなるように調整しておきます。
お布施の書き方
まずは表書きについて。
袋の中央に表書きを書く
封筒に印字されていない場合は、袋の中央上部あたりに「御布施」「お布施」「御礼」などの文字を書きます。
場合によっては「読経料」「戒名料」などと書く方もいるでしょう。
しかし、お布施は本来「仏様」へのお供え物です。そのため僧侶によっては、何らかの料金であることを連想させるような書き方を好まない場合があります。
そのため無難に「お布施」などと書いておけば大丈夫でしょう。
表書きの下に名前を書く
この表書きの下に名前を書きます。喪主の苗字かフルネーム、あるいは「××家」のように書きましょう。
裏書の書き方
続いては「裏書き」についてです。
封筒の裏側に「氏名・住所・電話番号・金額」を書きましょう。金額を書いておくと、僧侶側の事務的処理が簡単になります。
省略して金額だけを書いても構いません。基本的には縦書きで書いておきます。
数字は漢数字で書く
数字を書くときは漢数字を使うのですが、旧字体を使うのが一般的。昔は旧字体を使うことで数字の書き換えを防いでいたため、その名残が今でも残っているのです。
中袋に入れた場合
ちなみに中袋に入れた場合は、封筒に裏書きは書きません。中袋の表側に金額を書き、裏側の左下に氏名と住所を書きましょう。
渡し方・渡すタイミング
お布施を渡すのは、四十九日法要が始まる前、あるいは終わった後が一般的です。
しかし儀式開始前は喪主が忙しい場合が多いので、状況にもよりますが余裕のある終了後に渡した方が良いです。
僧侶が会食に参加する場合は、そのときに渡すこともあります。ここら辺のタイミングに関しては、事前に僧侶と話し合っておくとスムーズです。
お布施の渡し方のマナー
渡し方にもマナーがあります。そのまま封筒を手渡しすればいいわけではありません。
渡すまでは封筒を袱紗(ふくさ)に包みバッグに入れておきます。渡すタイミングでバッグから袱紗を取り出しましょう。
袱紗から封筒を取り出したら、それを小さなお盆に乗せます。「切手盆」を使うのが理想的です。
そして、封筒の文字が僧侶から読めるようにしながら、お盆を両手で差し出してください。
袱紗(ふくさ)の色
お盆が無ければ、袱紗を開きその上に封筒を乗せた状態で差し出せば大丈夫です。
その際、袱紗の色にも注意しましょう。袱紗は何色を使っても良いという訳では無く、葬儀や法要では落ち着いた色の袱紗の色を選ぶ必要があります。具体的には紫を使う方が多く、寒色系を選びましょう。
四十九日法要の引き物と香典返しについて
四十九日法要のときに、参列者からお供え物や香典をもらう場合があります。その際は、引き物や香典返しをお返しする必要があります。
引き物と香典返しに用意するもの
引き物や香典返しはできるだけ軽く持ち運びがしやすいものを選ぶようにしましょう。食品や消耗できる日用品が向いています。重たいもの、かさばるものは持ち帰る時に大変です。また、冷蔵品は避け常温で保存が効くものにしましょう。日用品は石鹸や洗剤がおすすめです。
最近では、商品券やカタログギフトを選ぶ方も多いようですが、金額がはっきりと分かる物はマナー違反と感じる方もいらっしゃいます。お渡しする相手が受け入れやすいものを選ぶ心遣いも大切です。
引き物と香典返しの費用相場
引き物、香典返し共に1/3から1/2程度が相場目安とされています。
四十九日法要後にお斎など会食を振舞う場合は、3,000~5,000円程度でも問題ありません。
はじめての葬儀なら「やさしいお葬式」
はじめて行う葬儀の準備に戸惑うのは当然のことです。特にお葬式の規模や形式には正解がないため、どのように見送ればよいか分からず迷い悩む方も大勢いらっしゃいます。
はじめての葬儀に不安や心配を感じている方は、ぜひ「やさしいお葬式」をご検討ください。
やさしいお葬式では、はじめての葬儀でも安心してお任せ頂けるよう下記「3つのやさしい」をお約束しています。
1.ご遺族にやさしい
当社の相談員の対応満足度は91%。専門知識を持つプロの相談員が、お葬式の手配や流れについてゼロからサポートいたします。
喪主が初めての方や、お葬式の流れに不安を感じる方でも安心してご相談ください。ご遺族に寄り添うグリーフケア研修を受けたスタッフが、公正中立な立場からご希望やご予算に合わせた最適なプランをご提案します。
2.お財布にやさしい
「高額」と思われがちな葬儀費用ですが、当社では必要な項目のみを厳選し、一般価格よりも低コストで、質の高いお葬式を実現しています。
さらに、事前の資料請求で最大5万円引きの割引特典も実施し、業界最安水準の税抜:75,000円(税込:82,500円)からのご葬儀を提供しています。
明朗会計で、追加料金や不明瞭な請求は一切ないため、ご遺族さまの経済的な負担を最小限に抑えます。
3.いつでもやさしい
24時間365日のサポート体制で、深夜や早朝でも即時対応が可能です。
日本全国3,500の斎場と提携しているため、ご希望の場所や地域でご葬儀が挙げられます。
生前のお葬式準備から、お葬式後の法事・法要、お墓の相談までいつでも相談可能です。
「やさしいお葬式」は、大切な方をお見送りするご遺族さまに心から寄り添い、公正中立の立場で最良のお葬式を提案させて頂きます。
ご相談や資料請求はすべて無料です。はじめての葬儀での不安や疑問があれば、どんなことでもお気軽にご相談・ご連絡ください。
四十九日法要のお布施についてのまとめ
以上が四十九日法要に関する内容の解説です。今回の内容を簡単にまとめておきましょう。
【四十九日法要とは?】
●四十九日法要とは、仏教における「忌日法要」の一つのこと。この四十九日法要は故人やご遺族にとって最も大切な日とされている。
【忌中とは?】
●「忌中」とは、故人が亡くなってから四十九日まで喪に服し、身を慎むための期間のこと。
●似たような言葉に「喪中」があるが、こちらの期間は忌中よりも長く、最大で1年間喪中になることもある。
●「忌明け」とは、上記の忌中や喪中の期間が終わること。この忌明けの日に四十九日法要を行うことがほとんどである。
【追善供養とは?】
●「追善供養」とは、生きている方が故人に対して供養を行う行為のこと。
●広い意味では、仏壇に手を合わせてお茶を供えたり、お墓参りをすることも追善供養の部類に入るが、一般的には「一周忌などの法要・法事を行うこと」そのものが追善供養と呼ばれる。
【宗派による四十九日法要の違い】
●四十九日法要の基本的な流れ自体に大きな違いはない。しかし細かい面では多少宗派に合わせる必要がある。
●ただし「仏教」「神道」「キリスト教」という大きな枠で考えると大きく違いがある。
【四十九日法要を行う際の注意】
●葬儀を終えたら、なるべく早めに日程と会場を決める。四十九日を迎える直前の休日がベスト。
●同時に会場も決めておく。自宅・寺院・斎場・ホテルなどを選ぶ方が多い。日程が決まり次第寺院に連絡する。
●僧侶の予定も関係してくるのでなるべく早めに伝えておくべき。
●四十九日法要後の会食の手配も忘れずに行う。参列してもらう方の範囲も決めておく必要がある。四十九日法要と合わせて納骨を行う方も多い。
【四十九日法要の流れ】
●四十九日法要当日は「開式の挨拶→読経とご焼香→僧侶の説話→位牌の閉眼&開眼供養→納骨とお墓参り→会食→香典返しやお布施を渡す」という流れで進める。
【四十九日法要のお布施】
●現代では、お布施を渡すことで供養を行ってくれた僧侶への感謝の気持ちを表現している。
●四十九日法要のお布施の相場は、葬儀形態に関わらず5万円前後が一般的。
●宗派ごとにお布施の相場は多少変動する。なぜなら宗派によっては卒塔婆や本位牌を準備する必要があるため。地域別でもそこまで大きな差は無いが、若干の変動はある。
●四十九日法要では、必要に応じてお布施以外の「御車代」「御膳料」「納骨法要に対するお布施」「御卒塔婆料」なども渡す。
【四十九日法要のお布施の包み方】
●お布施は、現金を「郵便番号欄の無い無地の白い封筒」あるいは「お布施」の文字が印刷された専用の封筒に入れて渡す。
●そのまま封筒に入れて渡しても問題はないが、奉書紙(ほうしょがみ)という白い紙で包むとさらに丁寧。
●お札は人物画が描かれている方を上に向け、袋の入り口側に人物画が来るように入れる。また、四十九日法要はすでに予定が決まっているのでなるべく新札を入れる。
【四十九日法要のお布施の書き方】
●表書きは、袋の中央上部あたりに「御布施」「お布施」「御礼」などの文字を書く。また「裏書き」として、封筒の裏側に「氏名・住所・電話番号・金額」を書く。
【四十九日法要のお布施を渡すタイミング】
●お布施を渡すタイミングは、事前に僧侶と話し合っておくとよい。
●お布施を渡すまでは封筒を袱紗に包みバッグに入れておき、渡すタイミングでバッグから袱紗を取り出す。
●袱紗から封筒を取り出したら、それを小さなお盆に乗せて封筒の文字が僧侶から読めるようにしながら両手で差し出す。
このように四十九日法要におけるお布施の金額は、葬儀・告別式とは多少変わってきます。
また、金額だけでなく渡すタイミングや渡し方にもマナーがあるので、僧侶に正しく感謝の気持ちを伝えられるようにこの辺りもしっかり覚えておきましょう。
<<お布施についてはこちらの記事も読まれています>>
・初盆(新盆)のお布施を完全解説!金額相場・渡し方・マナーを紹介!
・枕経とは?何のために亡くなった方へ枕経を行うのか、実際のお布施の相場とは
・墓じまいのお布施について、費用相場からマナーまでを徹底解説!
・永代供養料を完全解説!相場・手続きの流れ・お布施との違いを紹介!
・法事とは?日程とお布施と服装持物を徹底解説!
_1.png)
【監修】栗本喬一(くりもと きょういち)
- 略歴
- 栗本喬一(くりもと きょういち)
- 1977年生まれ
- 出生地:東京都(愛知県名古屋市育ち)
- 株式会社東京セレモニー 取締役
- ディパーチャーズ・ジャパン株式会社
- 「おくりびとのお葬式」副社長として、葬儀会社の立ち上げ。「おくりびとアカデミー」葬儀専門学校 葬祭・宗教学 講師。
- 株式会社おぼうさんどっとこむ
- 常務取締役として、僧侶派遣会社を運営。
- 株式会社ティア
- 葬祭ディレクター、支配人、関東進出責任者として一部上場葬儀 社の葬儀会館出店、採用、運営を経験。
- 著書:初めての喪主マニュアル(Amazonランキング2位獲得)
プロフィール









.jpg)
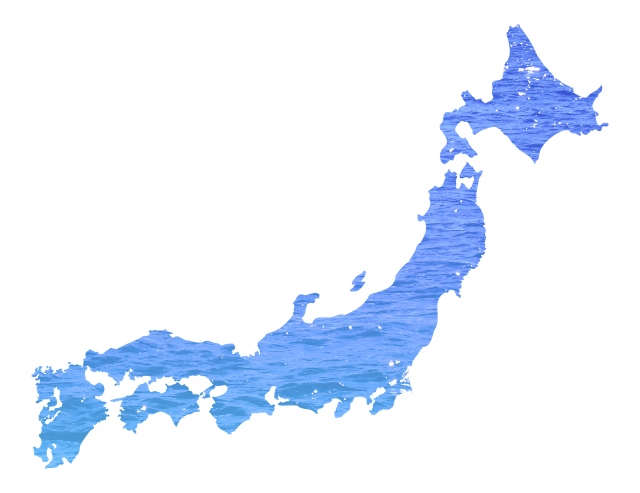
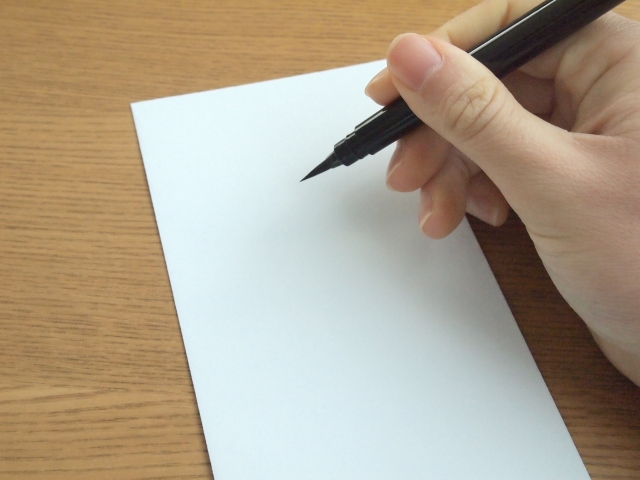
_1.png)










