喪中期間にしてはいけないこと一覧【年賀状・旅行・結婚式など】
喪中期間にしてはいけないこと一覧【年賀状・旅行・結婚式など】
──悲しみを、前を向く力に変えるために──
人が生きるということは、出会いがあり、別れがあるということ。
大切な家族を亡くしたあとに訪れる「喪中(もちゅう)」の期間は、決して“止まった時間”ではありません。
それは、これからをどう生きるかを静かに見つめ直す時間です。
この記事では、「喪中 期間にしてはいけないこと」を中心に、年賀状・結婚式・旅行などの具体的なマナーをわかりやすく紹介しながら、喪中を“心の再生期間”として前向きに過ごすヒントをお伝えします。

喪中とは?——悲しみを整理し、感謝を深める時間
「喪中」とは、家族や親しい人の死を悼み、一定期間お祝い事などを控える期間のことです。
しかし、形式的に「やってはいけないこと」を守るだけの時間ではありません。
本来の意味は、故人を想いながら、自分の心を静かに整える期間。
つまり、“悲しみを我慢するため”ではなく、“ありがとう”を見つめ直すための時間なのです。
喪中期間の目安
喪中の期間は明確に決められていませんが、一般的な目安は以下のとおりです。
| 故人との関係 |
喪中期間の目安 |
| 両親・配偶者 |
約12〜13か月 |
| 子ども |
約12か月 |
| 祖父母 |
約6か月 |
| 兄弟姉妹 |
約6か月 |
| おじ・おば |
約3か月 |
この期間を「一周忌」までとする考え方が多いですが、現代では「心の区切り」を基準にする人も増えています。
故人との絆が深ければ、期間にこだわる必要はありません。大切なのは、気持ちの整理をどうつけるかです。
喪中期間にやってはいけないこと一覧
——“控えること”が、優しさの形になる
喪中期間に控えるべきことは、「祝い事」「派手な行動」「新年の挨拶」などです。
ただし、これは“禁止”ではなく“思いやりの表現”。
故人を想い、周囲に悲しみを伝えないようにするための心のマナーです。
1. 年賀状を出すことは控える
「喪中 年賀状」は、最も多くの人が迷うテーマかもしれません。
新年の挨拶である年賀状には「おめでとう」「祝う」という意味が含まれます。
そのため、喪中期間中は年賀状を出さず、喪中はがきで「今年は年始のご挨拶を控えます」と伝えるのが礼儀です。
喪中はがきの出し方
- 投函時期:11月中旬〜12月初旬
- 内容:簡潔に「故人が○月に永眠したため、新年のご挨拶を控えます」と書く
- ポイント:形式よりも、相手への感謝の気持ちを込めること
もし年賀状が届いた場合は、「寒中見舞い」で感謝の言葉を返しましょう。
「お気遣いありがとうございました。寒さ厳しい折、お身体を大切にお過ごしください」
——この一言に、優しさと敬意がにじみます。
2. 結婚式や祝い事への参加・開催
「喪中 結婚式」は、多くの人が悩むテーマです。
一般的には、喪中期間中は祝い事を避けるとされています。
しかし近年では、「故人が喜んでくれるなら」と柔軟に考える人も増えています。
大切なのは“気持ち”です。
結婚式に招待された場合
- 四十九日(忌明け)までは欠席が望ましい
- それ以降であれば、控えめな服装で静かに出席するのも可
- お祝いの言葉や態度は、控えめで丁寧に
自分が主催する場合
- 喪中期間中の開催は避け、一周忌以降が望ましい
- やむを得ない場合は、身内と相談し、小規模・厳かな進行に
結婚式は人生の大きな節目です。
「悲しみの後に笑顔を取り戻す」ことも、故人への最大の供養かもしれません。
3. 派手な旅行・娯楽は控えめに
「喪中 旅行」も迷いやすいテーマです。
旅行そのものがいけないわけではありませんが、目的や雰囲気によって印象が変わります。
控えた方がいい旅行
- リゾート地での派手なパーティー旅行
- 大人数での賑やかな観光旅行
許される旅行
- 故人との思い出の地を訪れる
- お墓参りや法要を兼ねた家族旅行
- 心を癒す静かな温泉旅行
つまり、“悲しみから逃げるため”の旅行ではなく、“想いを整えるため”の旅であれば問題ありません。
4. 神社への参拝は忌明け後に
喪中と忌中は混同されがちですが、神道では「死」を穢れとみなすため、
四十九日(忌明け)までは神社への参拝を控えるのが一般的です。
忌明け後は、「これからも見守ってください」という気持ちで静かにお参りしましょう。
神様も、悲しみを乗り越えようとするあなたの心を受け止めてくれます。
5. パーティーや祝い事
誕生日会、忘年会、新年会なども、喪中の間は控えめに過ごすのが礼儀です。
ただし、「参加しない」と言うのではなく、
「今は静かに過ごしたい時期です」と穏やかに伝えると、相手にも誠意が伝わります。
喪中だからこそ気づける、“生きる力”
喪中は“失う時間”ではなく、“心を取り戻す時間”です。
静かな日々の中で、私たちは次のような気づきを得ることができます。
- 感謝の言葉を、今伝えることの大切さ
- 当たり前の日常が、どれほど尊いか
- 人はひとりでは生きられないということ
喪中期間は、これまでの人生を振り返り、「これからどう生きるか」を考えるチャンスでもあります。
悲しみを我慢するのではなく、悲しみを優しさに変える。
それが、喪中を前向きに過ごす第一歩です。
喪中期間に「してもいいこと」——心を育てる時間に変える
喪中だからといって、何もかも我慢しなければならないわけではありません。
「控えるべきこと」がある一方で、静かに心を癒す行動はむしろ良いとされています。
大切なのは、「故人を想う気持ちを忘れない」という姿勢。
その想いがあれば、あなたの一歩一歩が供養そのものになります。
1. 日常生活を普通に送る
仕事、家事、学業といった日常生活は、喪中でも続けて構いません。
むしろ、生活を整えることは「自分を立て直す行為」です。
たとえば、
- 朝、いつもの時間に起きる
- 家を掃除する
- 感謝の気持ちで食事をする
これらはどれも、故人が「元気でいてほしい」と願っていた姿に近づく行動です。
喪中 期間を生きることは、故人の願いを生きることでもあります。
2. お墓参りや法要への参加
お墓参りや法要は、喪中でも遠慮する必要はありません。
「喪中 期間」は、まさに故人を偲ぶための時間。
静かに手を合わせながら、「ありがとう」と心の中で語りかける。
それだけで、心が少しずつやわらかくなっていくはずです。
ときには、墓前で泣いてもかまいません。
涙は悲しみの証ではなく、愛がまだ生きている証です。
3. 旅行やお出かけも「癒し」としてならOK
「喪中 旅行」をどう捉えるかは、人によって意見が分かれます。
しかし、故人の思い出をたどるような旅や、心を休めるための静かな旅行であれば問題ありません。
たとえば、
- 故人が好きだった場所を訪れる
- 思い出の風景を写真に収める
- 山や海を眺めながら「生かされている」ことに感謝する
それは単なる旅ではなく、心のリハビリです。
「悲しみを癒す旅」こそ、喪中の時間を豊かに過ごす方法のひとつです。
4. 趣味や学びを通じて“心を育てる”
絵を描く、日記を書く、音楽を聴く、本を読む——
どんな形でも、自分の感情を表現することは大切です。
「喪中 やってはいけないこと」はたしかにありますが、
“心を閉じ込めること”はやってはいけないことの中でも一番避けるべきです。
悲しみも喜びも、あなたの一部。
それを丁寧に見つめることが、やがて前を向くエネルギーに変わります。
喪中明けの過ごし方——「再出発の日」にできること
喪中の期間が終わると、「明け」と呼ばれる時期を迎えます。
それは、故人が「もう大丈夫だよ」と背中を押してくれているサインかもしれません。
では、喪中明けをどんな気持ちで迎えればいいのでしょうか?
1. 感謝の手紙を書く
喪中明けには、感謝の言葉を形にするのがおすすめです。
亡くなった人に宛てた手紙でもいいし、支えてくれた家族や友人への手紙でも構いません。
書くことで、心が整理されます。
「生きる力をありがとう」と綴る時間は、喪中の締めくくりとしてとても意味があります。
2. 小さな“お祝い”を再開する
喪中中は結婚式や年賀状などの祝い事を控えますが、明けたあとは少しずつ再開して構いません。
初詣に行く、新しい服を買う、花を飾る——。
それはすべて「生きる喜びを取り戻す儀式」です。
悲しみの中から光を見つけることこそ、喪中明けにふさわしい第一歩です。
3. 故人を心の中で“共に生きる”
喪中を過ぎても、故人がいなくなるわけではありません。
あなたの記憶の中に、いつも寄り添ってくれています。
ふとした瞬間に、「これ、あの人ならどう言うかな」と思い浮かぶことがあるでしょう。
その瞬間こそ、故人とあなたの心がつながっている証です。
喪中は“別れの期間”ではなく、“共に生きるための準備期間”なのです。
喪中期間を前向きに過ごすための3つの習慣
最後に、喪中を「心を癒す時間」に変えるための3つの習慣をご紹介します。
① 感謝をひとつ書き出す
一日の終わりに、「今日ありがたかったこと」を一つノートに書いてみましょう。
どんな小さなことでも構いません。
「朝日がきれいだった」「友人が声をかけてくれた」——それだけで、心が少しずつ温まります。
② 故人の好きだった香りを取り入れる
お線香、コーヒー、花の香り。
香りには記憶を呼び覚ます力があります。
ふと香りに包まれる瞬間、あなたは故人と同じ時間を共有しているのです。
③ 自分を責めない
「もっとこうすればよかった」と自分を責めるのは自然なことです。
でも、故人はあなたを責めていません。
むしろ、「幸せになってほしい」と願っているはず。
喪中を生きるということは、その願いを叶えることでもあります。
喪中を経て、“生きる力”を取り戻す
喪中 期間は、人によって長さも感じ方も違います。
けれども、誰にとっても共通しているのは、愛する人を想いながら前に進む勇気が必要だということ。
「喪中 やってはいけないこと」を守るのは、形式ではなく“心を整えるため”。
「喪中 年賀状」を控えるのは、悲しみを尊重するため。
「喪中 結婚式」や「喪中 旅行」を控えるのは、静かに故人を想うため。
すべては、優しさのかたちです。
最後に——喪中は「終わり」ではなく「始まり」
喪中を過ごすあなたへ。
今、少しでも心が重たく感じるなら、それは自然なことです。
けれど、その悲しみの奥には、確かに愛があります。
それを思い出に変える時間こそが喪中の意味です。
故人の分まで笑うこと、誰かを大切にすること。
それが、あなたに託された“生きる使命”なのかもしれません。
喪中の静けさの中で、自分の心を見つめ直したあなたは、きっともう前を向けます。
そしてある日、そっと笑えるようになったとき——
それは、故人が「ありがとう」と微笑んでいる瞬間です。
関連記事
併せて読みたい基礎記事はこちら。
・法要の服装マナー(七回忌)
・お供え・表書き・のしの基本
・初盆の香典マナー
・十七回忌の意味と準備
ご相談は24時間365日
葬儀についての不明点は『やさしいお葬式』で24時間365日ご相談を承っています。電話・メールいずれも可能です。葬儀・相続の流れまで、専門スタッフがやさしくサポートします。
_1.png)






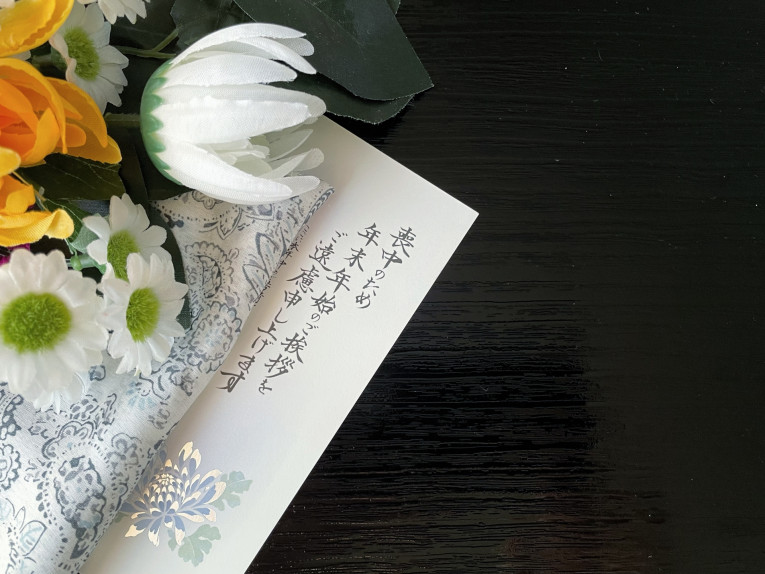

_1.png)







