神式葬儀での香典は「御玉串料」?表書きと金額相場
神式葬儀に参列することになったとき、多くの方がまず抱くのは「作法が分からない」という不安です。
仏式の葬儀とは異なる点が多く、香典にあたる「御玉串料とは何か」、表書き 書き方、のし袋 選び方、さらには金額 相場など、初めての人にとっては戸惑うポイントがいくつもあります。
しかし、実は神式の作法は決して難解ではありません。意味を理解すればするほど「気持ちを大切にする」優しい儀式であることが分かり、安心して参列できるようになります。
本記事では、初めてでも迷わないように、神式 香典の基本から玉串奉奠、心のあり方まで完全解説します。

御玉串料とは?神式の香典の意味を知ると安心できる
御玉串料とは?香典との違い
御玉串料とは、神式の葬儀で香典にあたる金品を指します。
仏式では香典によって「成仏を願う」意味が込められますが、神式では故人を「祖霊」として敬い、家族を見守る存在になるとされています。そのため、供物の表書きも「香典」ではなく「御玉串料」となるのです。
地域によっては「御榊料」「御神饌料」「御霊前」が使われるケースもありますが、葬儀参列時は「御玉串料」を選べば間違いありません。
御玉串料に込められた意味
玉串とは、榊に紙垂(しで)をつけたもので、神前で捧げる供物の一つです。御玉串料には、玉串に込められる「祈り」「敬意」「感謝」を金品という形にして遺族へ届けるという意味があります。
つまり御玉串料とは「故人を敬い、想いを伝える」ためのもの。金額の多寡よりも、気持ちが最も重要視されます。
神式の香典袋(のし袋 選び方)
水引は「白黒」または「双銀」を選ぶ
神式 香典ののし袋選びにはいくつかの注意点がありますが、基本はとてもシンプルです。
神式の水引は「白黒」または「双銀」の結び切りを選びます。
紅白は慶事用のため使用できません。神式でも仏式でも、弔事は「結び切り」が基本です。
のし(熨斗)は付けない
のしは祝い事の象徴となるため、弔事では適しません。のし袋にのしが印刷されている場合は、避けた方が無難です。
白封筒でもOK
地域によっては「水引なしの白封筒」が一般的な場合もあり、決して失礼ではありません。大切なのは形式よりも誠意です。
御玉串料の表書き 書き方
表書きは「薄墨」で書く
薄墨には「急な訃報で墨を十分にすれなかった」「悲しみで墨がにじんだ」という意味があり、神式でも広く用いられます。
表書きの種類
神式で使える表書きは以下の通りです。
・御玉串料
・御榊料
・御神饌料
・御霊前
迷ったときは「御玉串料」が最も無難です。
氏名の書き方
香典袋中央にフルネームで書きます。夫婦で参列する場合は、夫の左側に妻の名前をやや小さめに添える形が一般的です。
中袋の書き方(住所・金額)
金額は漢数字が丁寧
中袋には金額を記入しますが、丁寧な印象になるため漢数字(壱・弐・参…)が好まれます。
例:金 壱萬円
住所・氏名は裏面へ
香典返しの際に必要となるため、裏面に住所と氏名を記入します。
御玉串料の金額 相場
一般的な相場目安
神式の金額相場は仏式の香典と大きく変わりません。
友人・知人:3,000〜5,000円
会社関係:3,000〜10,000円
親族:10,000〜30,000円
両親:30,000〜50,000円以上
金額は関係性によるものなので、「無理のない範囲」で構いません。
金額より大切なのは気持ち
御玉串料は金額の大小が問われるものではなく、故人を想う気持ちそのものが尊重されます。
迷ったら「相場の中央の金額」を選ぶと安心です。
玉串奉奠(たまぐしほうてん)の作法
玉串奉奠は決して難しくない
神式の儀式で特徴的なのが玉串奉奠ですが、事前に流れを知っておくだけで驚くほど落ち着いて臨めます。
玉串奉奠の基本の流れ
1. 玉串を右手で根元を上から、左手で葉先を下から受け取る
2. 祭壇前に進む
3. 玉串を時計回りに回し、根元を手前にする
4. 玉串台に静かに置く
5. 二礼二拍手一礼(拍手は音を立てない「しのび手」)
6. 一礼して退く
初めてでも、司会者や神職が丁寧に案内してくれるため、構えすぎなくて大丈夫です。
大切なのは「正確さ」より「心の落ち着き」
玉串奉奠は、故人を想う静かな時間です。動きの細かい正確さよりも、心を込めることが最も重視されます。
神式の香典の渡し方・声かけ
受付での渡し方
神式でも、受付で御玉串料を渡す流れは仏式と同じです。
声かけの例
・「このたびはご愁傷さまです」
・「心よりお悔やみ申し上げます」
特別な神式独自の挨拶をする必要はありません。
遺族が最も嬉しいのは「参列してくれたこと」
形式以上に、あなたが足を運んだその行動こそが、遺族の心を支えます。
神式葬儀が大切にする心のあり方
神式は“静かに寄り添う祈り”
神式では、故人を祖霊として崇め、これからも家を見守っていく存在として敬意を払います。静かな所作の中に、日本古来の美しい価値観が込められています。
作法はすべて「気持ち」を形にしたもの
・玉串を回す動き
・しのび手
・二礼二拍手一礼
これらはすべて、故人を敬う気持ちを表現した所作です。
難しさを感じたときほど「意味」を知ると心が軽くなる
作法の背景にある意味を理解すると、「間違えたらどうしよう」という不安より、「心を込めたい」という思いが自然に上回るようになります。
読後に前向きな態度変容が起きる参列者のポイント
① 知ることで不安は小さくなる
御玉串料とは何か、のし袋 選び方、金額 相場、表書き 書き方――これらを理解しただけで、心の準備はほぼ整っています。
② 完璧を求めず「誠意」を大切にする
参列者としての姿勢で最も重要なのは、形式に囚われすぎず、故人と遺族への誠意を持つことです。
③ 故人を想う静かな時間を大切にする
作法に気を取られるよりも、故人との思い出を胸に手を合わせることが、最も美しい参列になります。
まとめ:神式葬儀は“難しい儀式”ではなく“心が整う場”
ここまで、神式 香典の基本から御玉串料、のし袋 選び方、金額 相場、表書き 書き方、玉串奉奠の流れ、心の在り方まで総合的に解説してきました。
神式は「作法が難しそう」と思われがちですが、本質はとてもシンプルです。
神式葬儀は、静かに故人を想い、自分の心が落ち着いていく時間をもたらす温かい儀式です。
この記事を読み、「これなら私も落ち着いて参列できる」と思えたなら、それこそが前向きな態度変容の証です。
自信を持って参列してください
あなたが心を込めて準備し、故人を想って手を合わせる――その行為自体が何よりの供養になります。
御玉串料の金額や作法の細かさより、気持ちが最も尊ばれる。それが神式の良さです。
どうか安心して、故人との最後の時間を大切にお過ごしください。
この記事を読んだ人におすすめの記事
・神式葬儀の作法を完全解説!玉串奉奠の意味と流れ
・香典袋の正しい書き方:仏式・神式・キリスト教の違い
・葬儀マナー全まとめ:服装・香典・挨拶・参列の心得
_1.png)






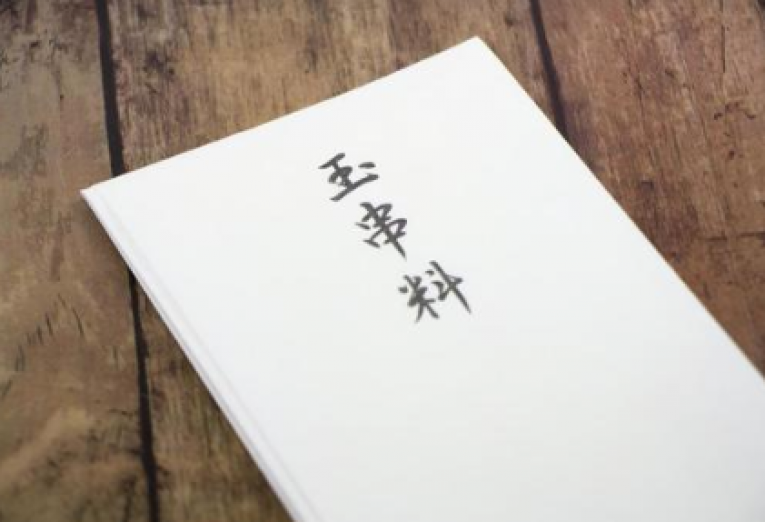

_1.png)







